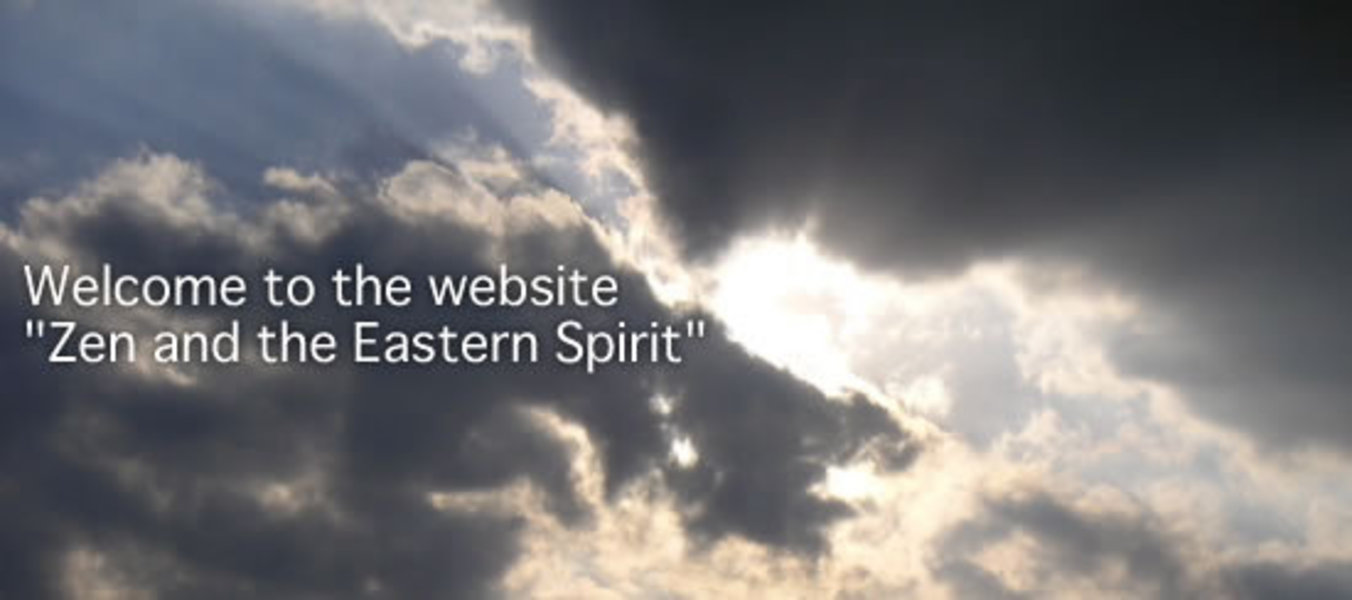着物の聖地 名勝庭園「光雲寺」
光雲寺の実質的創設者は東福門院。
光雲寺は東福門院の菩提寺。
東福門院は今の着物文化の創始者。
江戸初期に、宮廷ファッションを十二単から小袖に替えた。
宮中のカジュアルウェアー (普段着)に小袖を着用する習慣を持ち込み、その後さらに完成度を高めていった着物文化の最大の貢献者。
Update Date : 2022-11-30 01:14:07
この記事をシェアしてください。 ☺
●東福門院は今の着物の創始者
光雲寺の実質的創設者である東福門院は、宮廷ファッションを十二単から小袖に替え、今日の着物文化の基礎を創った最大の功労者である。
宮中でのカジュアルウェアー (普段着) を小袖着物ファッションに変貌させる。
宮中に小袖を着用する習慣を持ち込み、その後さらに完成度を高めていく着物文化の最大の貢献者。
嫁入りしてから亡くなるまで多くの衣装を手がけ、衣装代総額は50億円にも達するともいわれている。
東福門院は、これらの衣装を雁金屋(浅井長政の家来筋であった二代目道柏が、長政3人娘である淀君、京極高次夫人、徳川秀忠将軍夫人お江の方の着物制作を一手に引き受けていた)に発注し、デザインや意匠、加工方法等を事細かに指示したと伝わる。
雁金屋は東福門院和子の注文を実現するために意匠や染織技術の工夫を重ね、結果きもの文化の発展に大きく貢献した。
東福門院和子のデザインは「寛文小袖」といわれる模様形式を生みだし、1つの時代を確立した。
何しろその注文の数が中途半端ではなく、宮中に輿入れした3年後の元和9年(1623年)には小袖45点、染物14反、あわせて銀7貫866匆(もんめ)、現在の価格で800万円くらいの衣装代を雁金屋に支払っている。
小袖を多く発注し、宮廷ファッションの十二単を小袖に替えてしまったのは東福門院和子といわれるほど、その影響力は大きいものだった。
亡くなった延宝6年(1678年)、すでに72歳でしたが、なんと半年間に346点を注文し、いまの金額で1億6000万円相当
雁金屋で生まれた尾形光琳と乾山兄弟は、江戸時代の琳派の中心的存在となる。
アクセス
光雲寺へのアクセス
〒606-8446
京都市左京区南禅寺北ノ坊町59
市バス:東天王町で下車(徒歩約5分)
35.016909717211746
135.79482008703056
0
0
0
15
35.016909717211746,135.79482008703056,0,0,0
●名勝庭園「光雲寺」
多くの観光客で混雑している観光名所の南禅寺や永観堂の北側背後に、光雲寺はひっそりと佇みます。
東山・哲学の道を借景に琵琶湖疎水を引き込み、水の流れだけが響く静寂の庭。
七代目小川治兵衛作の池泉廻遊式庭園です。
この庭園を書院の縁側から座って見ていると、ついつい時間を気にせずに座っていたくなります。
●光雲寺
臨済宗大本山 南禅寺 境外塔頭。
二代将軍 徳川秀忠と江の娘で、後水尾天皇の中宮となった「東福門院 徳川和子」の尽力で菩提寺として再興。
本尊は、東福門院の釈迦如来と観音菩薩を安置。
歴代皇室の尊崇もあつく、久邇宮家(くにのみやけ)の菩提所。
紅葉の光雲寺
2019年11月25日 紅葉の光雲寺
OpenMatome
2019年11月23日 紅葉の光雲寺
撮影時刻は、15:30頃です。
Photo by Tigertakashi.
OpenMatome
七代目小川治兵衛作の池泉廻遊式庭園
Maiko_20190630_121_4
【Maiko, June 30, 2019】
Maiko is Kanohisa.
Shooting location is Kouunji-Temple.
Photo by k.sumika.
【舞妓, 2019-06-30】
舞妓は叶久さんです。
撮影場所は光雲寺。
Photo by k.sumika.
Maiko_20190630_66_12
【Maiko, June 30, 2019】
Maiko is Kanohisa.
Shooting location is Kouunji-Temple.
Photo by H.TOMOTOSHI.
【舞妓, 2019-06-30】
舞妓は叶久さんです。
撮影場所は光雲寺。
Photo by H.TOMOTOSHI.
Maiko_20190630_66_15
【Maiko, June 30, 2019】
Maiko is Kanohisa.
Shooting location is Kouunji-Temple.
Photo by H.TOMOTOSHI.
【舞妓, 2019-06-30】
舞妓は叶久さんです。
撮影場所は光雲寺。
Photo by H.TOMOTOSHI.
明正天皇寄贈の鐘
Maiko_20190630_128_23
【Maiko, June 30, 2019】
Maiko is Kanohisa.
Shooting location is Kouunji-Temple.
Photo by AnousTW.
【舞妓, 2019-06-30】
舞妓は叶久さんです。
撮影場所は光雲寺。
Photo by AnousTW.
【背景の鐘】
明正天皇寄贈の鐘
明正天皇(めいしょうてんのう)
女帝(女性天皇)
1624年1月9日 - 1696年12月4日
第109代天皇(在位:1629年12月22日 - 1643年11月14日)
父:後水尾天皇の第二皇女。
母:太政大臣征夷大将軍徳川秀忠の娘・東福門院源和子。
母方の伯父は徳川家光。
半夏生の光雲寺
Maiko_20190630_66_17
【Maiko, June 30, 2019】
Maiko is Kanohisa.
Shooting location is Kouunji-Temple.
Photo by H.TOMOTOSHI.
【舞妓, 2019-06-30】
舞妓は叶久さんです。
撮影場所は光雲寺。
Photo by H.TOMOTOSHI.
【フォト俳句賞】
『舞妓の影池塘彩なす半夏生』
by さくらがい
Maiko_20190630_32_1
【Maiko, June 30, 2019】
Maiko is Kanohisa.
Shooting location is Kouunji-Temple.
Photo by Hirokuni_Doi.
【舞妓, 2019-06-30】
舞妓は叶久さんです。
撮影場所は光雲寺。
Photo by Hirokuni_Doi.
見ごろの桔梗
2019年6月30日撮影
OpenMatome
光雲寺と人
光雲寺
光雲寺(山号・霊芝山)は臨済宗大本山南禅寺の境外塔頭。
開山は南禅寺と同じく、大明国師(無関普門禅師)で、弘安3年(1280)。
南禅寺の開創に先立つこと、11年。
その後、京都を勃発地として10年続いた応仁の大乱のため荒廃したが、寛文4年(1664)に南禅寺第280世英中玄賢禅師により、後水尾天皇の皇后である東福門院様の菩提寺として、現在の南禅寺北ノ坊の地に移して再興された。
当初は5,300坪の広大な寺域で50人の雲衲が切磋琢磨していたと伝えられている。
鐘楼は、東福門院の第一皇女、明正天皇の寄進。
京都市指定の文化財は仏殿と鐘楼以外に、古文書など330点以上を有す。
・京都市名勝:庭園(七代目小川治兵衛作庭)
・京都市指定文化財:東福門院坐像
東福門院(とうふくもんいん) - Wikipedia
徳川 和子(とくがわ まさこ・かずこ、慶長12年10月4日(1607年11月23日) - 延宝6年6月15日(1678年8月2日))は、徳川秀忠の娘(五女)で、徳川家康の内孫。
後水尾天皇の中宮。
明正天皇の生母。
また女院として東福門院(とうふくもんいん)。
御所でも仏頂国師(一絲文守禅師)の説法に感銘を受けられ禅宗に帰依された東福門院は、光雲寺を英中禅師の推挙によりご自分の菩提寺として再興するに際して、父君である秀忠公の遺金を以てされました。光雲寺の再興のために東福門院様から拝領したお金は、判金200枚と小判2千両で、これは約四千数百石に相当します。
紫衣事件などでご主人の後水尾天皇と父君である秀忠公との確執の板挟みになられ言語を絶するご苦労がおありだったと拝察されますが、ご夫婦仲は良く、7人のお子様を授かられました。残念ながら2人の親王様(男のお子様)は夭折され、徳川家の血筋を天皇家に残すことは叶いませんでしたが、女一の宮の興子(おきこ)内親王は奈良時代以来、860年ぶりの女性天皇である明正天皇となられました。
http://rakudo.jp/history
昭子内親王 - Wikipedia
後水尾天皇の第四皇女。母は東福門院。幼名を女三宮という。
寛永14年(1637年)12月8日、内親王宣下を受け、名を昭子内親王とされた。
生涯独身で、寺院への入室もなく、主に女院御所内の御殿において両親のそばで生活した。寛永年間に内親王のために岩倉に山荘が築かれ、岩倉御所と称された。出家はしなかったが、仏道へ傾倒するところもあったらしく、異母姉の文智女王とも親しく交流していたようである。
延宝3年(1675年)、両親に先立ち死去。享年47。戒名は妙荘厳院。墓所は光雲寺。
東福門院は、女三宮の昭子内親王が延宝3年(1675)に先立たれると、その葬儀を光雲寺で執り行うように手配され、墓所を光雲寺境内に定められたのです。
光雲寺には御所から光雲寺へのご行列の次第が記されたその当時の貴重な記録が残っております。
また女三宮の御殿のひとつが住持である英中禅師の住まいとして移され、その戒名と同じく「妙荘厳院」という名が特別に許可されました。
東福門院はその身分の高さから、自由な外出が叶わず、菩提寺の光雲寺にも臨行することはできなかったようですが、側近の家臣や女房たちを通じて、色々な寺宝を奉納したり、祈願や法要などを依頼されたりし、また英中禅師が出世したときや江戸徳川将軍家に赴く際などには祝儀を届けさせられるなど、絶えず濃やかな心配りをされたのです。
光雲寺の住職・田中寛洲さん
Zen and the Eastern Spirit
For several thousand years the eastern classics contained in this website have been carefully preserved and respected as spiritual food for the hearts of our predecessors. The Zen way of life is a profound state of mind, that has been passed down from master to disciple.
We created this website so that people all over the world can recognize the “Eastern spirit” again.
It is our humble wish that it will help you on your spiritual journey.
Peace and prayers,
Kanju Tanaka
About Author
Kanju Tanaka
Born in Osaka in January 1948
Received a MA in Philosophy studying German philosophy at Kyoto University
Instructed by Master Shonen Morimoto for three years while in university
Trained at Myoshinji, Kenchoji, Kenninnji monasteries and at Sogenji temple
Finally received dharma transmission from Master Sonin Kajitani at Shokokuji monastery
[An Additional Note]
Thankfully, I've been appointed as the chief priest at Kouunji-Temple, which is located just 15 minutes from Nanzenji-Temple. There is a large Main Hall(meditation hall), built 340 years ago, which is used for services and as a Zazen Hall. At former temple we were only able to sit 20 or so students. Now, we can sit more than 50 people. Please come and see us whenever you visit Kyoto.
この記事をシェアしてください。 ☺
| 舞妓さんのゴールデンホホバ |
|---|
 保湿力。✔美白、アンチエイジング ✔クレンジングから洗顔後のお手入れまで、これ1本でオールインワンオイル ✔髪、頭肌のケア、爪の保湿 ✔肌荒れ、乾燥肌などのお肌の悩み解決 |
| 関連記事 |
|---|
 1 1
|
 2 2
|
 3 3
|
 4 4
|
 5 5
|
| Maiko SNS |
|---|
SNSで舞妓さん撮影会の情報発信中    |
| 人気のある記事 |
|---|
 1 1
|
 2 2
自動車運転免許の最高峰 けん引第二種免許とは
|
 3 3
|
 4 4
|
 5 5
寒咲のサクラ特集 ~秋から冬に開花するいろんな桜|MKタクシー
|