三輪 チサ・作『うちでとこづち』~ガラシャ物語より
天正十年六月十三日未明。秀吉軍足軽大将堀尾可晴(ほりおよしはる)は、渾身の力で宝積寺(ほうしゃくじ)の門扉を叩いた。
「羽柴様の命を受け、天王山山頂に向かう隊である。門を開け、ここを通されよ!」
ややあってそろそろと門を開けた僧侶たちは、流れ込む足軽隊の勢いに押され、逃げるように道を空ける……
Update Date : 2017-02-18 21:44:41
この記事をシェアしてください。 ☺
三輪 チサ・作『うちでとこづち』~ガラシャ物語
うちでとこづち
ガラシャ物語『うちでとこづち』
著:三輪 チサ
カバーイラスト:近藤 宗臣(そうしん)
『ガラシャ物語全集』は、京都フラワーツーリズムが提供する「まちおこし小説」の一環として出版されています。
kyoto.flowertourism.net/
天正十年六月十三日未明。秀吉軍足軽大将堀尾可晴(ほりおよしはる)は、渾身の力で宝積寺(ほうしゃくじ)の門扉を叩いた。
「羽柴様の命を受け、天王山山頂に向かう隊である。門を開け、ここを通されよ!」
ややあってそろそろと門を開けた僧侶たちは、流れ込む足軽隊の勢いに押され、逃げるように道を空ける。真っ先に飛び込んだ可晴は、本堂前に初老の僧を認め駆け寄った。
「御住職か。我らは何としても明智軍より先に山頂に着かねばならぬ。一刻を争う。山道をよく知る者の案内を請いたい」
はて、と老僧は周囲に立ち竦む僧たちに目をやるが、皆怯えたように首を振る。僧たちの夜着の裾から覗(のぞ)く脛(すね)は、一様に白く細い。脅して無理に同行させたところで、どのみち山頂までは駆け上がれまい。可晴は深い溜息を吐くと、「登り口は」と問うた。老僧が指す本堂右手奥に向かおうとしたときである。
目の端に、ちらりと動くものが映った。「何奴」可晴は反射的に刀を抜き、欄干下に突き入れた。ひゃあ、という高い声がして、ひとりの男童が転がり出てきた。慌てて逃げようとする童を、背後の足軽が首根っこを掴み取り押さえる。
「小童、こんな刻限に何をしている。さては小金で雇われ、様子を探っておったか」
数えで十一、二才位だろうか。童はどんぐり眼を見開くと、ふるふると首を振った。
「ウチデとコヅチに餌をあげていたんだよ。床下でこっそり飼っているんだ」
薄汚い小袖の懐から、二匹の子猫が顔を覗かせる。可晴ははっとして童に顔を寄せた。
「おまえ、山頂に上がる道を知っておるか」
童はふんと鼻を鳴らし、痩せた胸を反らせた。
「もちろんさ。山はおいらの庭だもの。目をつぶっていたって上がれるよ。でも――」
値踏みをするように、可晴を上から下までしげしげと見る。
「ええい、褒美なら無事山頂に着いたらたんまりやるわい。どこぞの城で使ってもらえるよう、頼んでやってもよい。どうだ、猫どもと一緒に暮らせるぞ」
本当か、というなり童は一目散に駆け出した。可晴は足軽たちと共に、その後を追った。
うねうねと蛇行する道は、ひどくぬかるんでいた。童の背中を見失うまいとすると、石や木の根に足を取られる。可晴をはじめ後続の足軽たちも、何度も手をつき膝をつき、半身どろどろになりながら走った。時おり雨粒がぱらぱらと葉を叩くが、男たちの体を冷ますには足りない。むしろ湿った空気に、汗が吹き出す。急な勾配を、童は野うさぎのように軽々と駆け上がる。その後ろを、屈強な男たちがひいひいと喘ぎながらよじ登っていく。陣笠(じんがさ)と胴鎧(どうよろい)だけの軽装であったが、それすら脱ぎ捨てたくなる。鉄砲を結えた紐が肩に食い込む。部下を励ます言葉もとうに出なくなり、可晴は童の後を黙々と上り続けた。
「ほら、ここから下がよく見えるよ。山のてっぺんより眺めがいいんだ」
松の木の脇で立ち止まり、童は可晴を手招いた。童の横に立ち、可晴は息を飲んだ。薄明るくなってきた空を映し、銀色に輝く三本の川が合流して一本の大河となっている。その左岸を埋め尽くす大軍は、最後尾が山の陰になって見えない。
このとき秀吉軍は、方々からの援軍を受け三万六千に膨らんでいることを可晴は知らない。ただ巨大な黒い龍が身をうねらせ、大河に寄り添い横たわっているように見えた。龍の頭の先、細い支流河川を挟んで陣を張る明智軍は、秀吉軍の半分にも満たない。対岸には、手を伸ばせば届きそうな男山。二本の川の中島、その先に広がる碁盤の目――あれが京。天王山を制するものが天下を制す。可晴は秀吉の意図を思い知り、ぞくりと身を震わせた。
「小童、名は何という」可晴は景色を見つめたまま問い掛けた。「りゅうじん」という童の声に、可晴ははっとして脇を見た。微笑む童の姿は足元から次第に薄くなり、やがてかき消すように失せた。
戦は秀吉軍の大勝に終わり、万を超える屍(しかばね)を残して退いた明智光秀は、後日小栗栖(おぐりす)の藪で農民に討たれた。天王山山頂を制した可晴は、続く関ヶ原の合戦でも功を上げ、後に秀吉の家老にまで上る。
当時秀吉の陣が敷かれ、後に改修された宝積寺、通称「宝寺」。龍神が聖武天皇に授けたといわれる「打出と小槌」が、今も宝物として納め祀(まつ)られている。
〈了〉
物語の舞台
宝積寺(小槌宮)
34.895300489164434
135.67853495434974
0
0
0
13
34.895300489164434,135.67853495434974,0,0,0
ガラシャ物語全集
「ガラシャ物語」とは
「ガラシャ物語」は、長岡京市、宮津市、京丹後市、亀岡市、福知山市、大山崎町、舞鶴市の七市町のいずれかを舞台として、ガラシャ、光秀、幽斎、忠興のいずれかを描いた短編小説シリーズです。
「小説・文学の力によるまちおこし」を目指しています。
ガラシャ物語全集 - OpenMatome
Amazon.co.jp: ガラシャ物語全集/京都フラワーツーリズム編 eBook: 花房観音, 宮木あや子, 安部龍太郎, 斎藤肇, 遠藤徹, 小林泰三, 寒竹泉美, TaMa, 京都フラワーツーリズム: Kindleストア
物語の舞台:宝積寺
宝積寺 - Wikipedia
724年、聖武天皇の勅命を受けた行基による開基と伝える。
聖武天皇が夢で竜神から授けられたという「打出」と「小槌」(打出と小槌は別のもの)を祀ることから「宝寺」(たからでら)の別名があり、大黒天宝寺ともいう。
天正10年(1582年)、天王山が羽柴秀吉と明智光秀が戦った山崎の戦いの舞台となり、その際宝積寺には秀吉の本陣が置かれた。直後秀吉により天王山に建設された「山崎城」にも取り込まれ、このため城は「宝寺城」とも呼ばれた。元治元年(1864年)には禁門の変で尊皇攘夷派の真木保臣を始めとする十七烈士らの陣地がおかれた。
「三輪 チサ」さんの作品
Amazon.co.jp: 三輪 チサ
三輪チサ - Wikipedia
「黒四」で第1回『幽』怪談実話コンテスト大賞受賞。
『死者はバスに乗って』で第5回『幽』怪談文学賞・長編部門大賞受賞(メディアファクトリー)。
この記事をシェアしてください。 ☺
| 舞妓さんのゴールデンホホバ |
|---|
 保湿力。✔美白、アンチエイジング ✔クレンジングから洗顔後のお手入れまで、これ1本でオールインワンオイル ✔髪、頭肌のケア、爪の保湿 ✔肌荒れ、乾燥肌などのお肌の悩み解決 |
| 関連記事 |
|---|
 1 1
|
 2 2
|
 3 3
|
 4 4
|
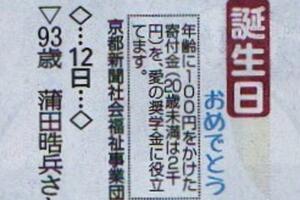 5 5
|
| Maiko SNS |
|---|
SNSで舞妓さん撮影会の情報発信中    |
| 人気のある記事 |
|---|
 1 1
iPhoneを縦向きで動画撮影したときの編集方法
|
 2 2
|
 3 3
自動車運転免許の最高峰 けん引第二種免許とは
|
 4 4
京都で生まれ京都で育った酵素浴「京の酵素浴」:ヒートショックプロテイン(HSP)入浴
|
 5 5
寒咲のサクラ特集 ~秋から冬に開花するいろんな桜|MKタクシー
|


